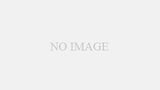自転車に乗れるようになるのは何歳頃?
補助輪なしで自転車に乗れるようになる平均年齢は6歳前後のようです(筆者調べ)
もちろん個人差はあると思います。
我が息子は自閉症スペクトラムで運動発達遅滞があり縄跳びや鉄棒ができません。
チャレンジ精神がなく、失敗することを極端に恐れ自信があることしかやりたがりません。
そんな息子が補助輪なしで自転車に乗れるようになったのは5歳7カ月頃。
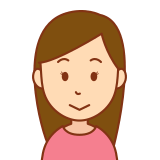
運動が苦手なのに早い方だよね…。
乗れるようにになったのは嬉しいけれどなんでだろう?
そもそもこの年齢だとどんな運動ができるようになるの?
5歳~5歳6カ月頃にできる運動とは?
・自転車や竹馬→平地で足や手を交互に動かすような運動
・上り棒→垂直な棒を登ったり降りたりする動き(支えありでも可)
・とび箱、側転→動作が3ステップ必要となるもの
・つま先立ちや片足立ち→・不安定な姿勢での静止制御
息子がこの時期にできていたのは上り棒(かなりの支えあり)と片足立ちが数秒できる位でした。
自転車が乗れるようになった理由とは?
運動が苦手な息子はなぜ自転車に乗れるようになったのだろう?
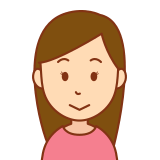
ストライダーに乗っていたから?

ストライダーは1歳半から乗ることができます。
ストライダーは子どもが直感的・本能的に操作できる構造になっているそうです。
【ストライダーの注意事項】
・ストライダーは公道走行禁止です。(遊具に該当するため)交通が頻繁な道路も走行禁止です。
・必ずヘルメットを着用しましょう。
・保護者同伴で遊びましょう。
(公式ホームページより)
息子の場合ですが、
いきなり補助輪をつけて自転車で練習するよりはまず、ストライダーで足漕ぎをしながらハンドル操作やバランス能力が鍛えられたようです。
とはいえ、ストライダーに乗れるようになったのも4歳過ぎた頃だったでしょうか。
せっかく購入しても乗ってみたいという興味は全く持たず、外に出れば虫探しにいそしむ日々…
パパがなかば強引にストライダーの練習させてましたが、最初は怖がってばかりでした。それでも少しづつハンドル操作ができるようになり、自分でもできる!となれば楽しいのでしょう。
自分から「ストライダーに乗りたい」と言うようになりました。
それからはひたすらストライダー乗りまくり。そろそろ自転車の練習をしてもよい頃になっても、2~3歳位の小さい子達に交じって公園で乗り回していました。(必ず付き添い、周囲の安全を確認しながら遊ばせています)
ストライダーなら乗れる!という楽しさや自信もついてきた頃、いよいよ自転車の練習をさせることにしました。
はじめはもちろん補助輪付きで。乗ること自体は嫌がることなくすんなりサドルにまたがりました。補助輪がついていれば転ぶことはないのでその恐怖はないでしょう。問題はペダルを漕ぐという動作。感覚がつかめないとうまく漕げません。
ペダルを漕ぐにはペダルを足の裏で押しながら回すイメージだと思うのですがそれが難しい。
息子にとってペダルに乗せた足をどう動かせば漕げるのか分からずひたすら斜め前に足を踏み出そうとしていたようです。
ペダルに乗せる足の位置が土踏まずやかかとに近い部分だったこともうまく漕げない理由だったようです。
失敗を恐れる子どもへの教え方
息子のような失敗を恐れるタイプは、自分にできそうだな、と思えば興味をもつし、できなそうだと思えば他の子ども達が楽しく遊んでいても全くヤル気にならない傾向にあります。
パッと対象物を見て、自分にできる、できないを判断しているようです。
こういうタイプにさせてはならないのは失敗してしまうこと。
なるべく失敗しないように小さなことから始め、褒める。褒めて成功体験をすることで自信をつけさせる。
可能な限り失敗させないこと。これには親がわが子ができそうなこと、できなそうなことの判断力も必要になってくるかと思います。
そして、小さな成功から次のステップへとうつり、だんだんと完成に近づけていく。
【自転車練習の進め方】
①はじめは補助輪付きでハンドルを一緒に持ちながら進めて自転車が動く感覚をつかむ。
②ペダルがうまく漕げない息子の足を持ち一緒に漕いで漕ぐ感覚をつかむ。
③少しずつです。1日でやろうとせず、何日も数カ月単位で気長に練習します。
④自分で漕げるようになったら周囲に十分気をつけて公園や安全な道でたくさん練習します。
⑤ブレーキをかけて両足を地面につけて止まる練習もします。
⑥十分に練習して本人に自信がついたらいよいよ補助輪を外します。
あとはテレビドラマでよくあるような「後ろ持っててあげるよ」と言って自然に手を離すやり方です。
失敗を恐れる子どもへの声掛け~注意すべきこと~
失敗を恐れている時への声掛けとして「失敗してもいい」
「はじめからできる人はいない、みんなはじめは失敗する」ということを伝えます。そして小さな成功体験を引き出して「さっきのこれができたから大丈夫、すごいよ」と褒めます。
このタイプは叱咤激励的な厳しめな指導をするともう二度とやらない!となってしまいます。要注意です。ヤル気を復活させるのが絶望的になる場合もあります。
とはいえ、気が散りやすく、やり方を教えている最中に虫を探し始める…など他のことに注意が移ってしまうとイライラしてしまい、厳しい口調になってしまいます。
親の忍耐力も試されますね。私はすぐイライラして厳しい口調になってしまいます。反省です。
まとめ
・ストライダーでたくさん遊び、体幹・バランス能力をつかむことができた(息子の場合) ・失敗させないことが大切(親が手伝ってもいいので成功した感覚を覚えさせる) ・小さな成功体験を積み上げる ・自信を持たせて次のステップへ移る ・気長に長期戦で行うことを心がける
運動発達遅滞があり、失敗することを極端に嫌う息子の例をあげました。
少しでも参考になれば幸いです。