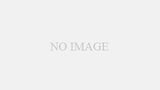梅雨時期の6月、この時期になると登園拒否がひどかった我が息子の保育園年中時代を思い出します。
この記事では
・子どもの登園しぶり、登園拒否に悩んでいる。 ・実際の体験談を読みたい。 ・解決方法を知りたい。
そのような方へ少しでも参考になればと思います。我が家の体験談です。
先にお話しすると、療育と保育園との併用で登園拒否を解決しています。
登園拒否はいつから始まった?
息子が1歳になり仕事に復帰した私は、息子を職場内の保育所に預けました。
先生に預けて私が立ち去るときも泣くことはなく、スムーズに引き渡すことができていました。
今思えば、その頃は後追いもしなかったのでママと離れるという状況がよく分かっていなかったのでしょう。
3歳を過ぎ、年少となった頃、ようやく状況を理解できるようになったのか、しぶるようになってきました。発達に遅れがあった息子は、簡単な言葉は言えたものの会話ができるほどの言語能力はありませんでした。
6月、保育園の駐車場に着き、車から降ろそうとすると嫌がって泣いて暴れていました。抱っこしてしまえばいいのですがチャイルドシートから降ろそうとしても私の腕をすり抜けてしまい、抱えることができませんでした。どうにもならないので少しドライブしたら気持ちが変わるかもと思い、状況を保育園と職場に電話し状況を伝え遅刻させてもらいました。近くをドライブし、車から降ろすとき、やっぱり嫌がりましたが先生が車まで迎えにきてくれました。
園の駐車場に着くと泣いて暴れて無理やり抱っこして先生に預ける…そんな日々が続いていました。
保育園に行ってしまえば、初めは少し泣いていたそうです。しばらくすると普通に楽しんで過ごせていたそうで先生方のおかげです。
6月を過ぎ、7月になると登園しぶりは少しずつ落ち着いていきました。
そして8月、年少の夏に地域の保育園に途中入園しました。
入園に際し、発達が遅れているなど心配なことを園に事前に説明していました。理解ある担任の先生のおかげで少ししぶりはあったものの、それほど心配になるほどではありませんでした。ここでも登園してしまえば嫌がって泣くようなことなく過ごせていたようです。
本格的な登園拒否のはじまり
年中に進級し、担任の先生も変わり、過ごす教室も変わり、変化の苦手な息子にとっては一大事だったのでしょう。5月の大型連休が終わったころからしぶりはじめ、6月に入ると本格的な登園拒否が始まったのです。
会話もできるようになってきた息子は帰ってくるなり「明日保育園行かない!」と言うようになりました。
さらには日曜日の朝になると目覚めてすぐ「明日は保育園?行きたくない」と大泣きしてしまうようになっていったのです。毎週続いていました。休みにお出かけしてもふとした時に「明日保育園?」と言い、表情も暗く青ざめていて笑顔がなくなっていました。
家を出る時間になると「保育園行かない」と寝室に逃げ込み泣いている息子。
私も仕事を休むわけにはいかない。それでなくても熱を出しやすい息子の看病のために休むことが多かった私は職場に迷惑をかけたくないと必死でした。
泣いている年中児を車にむりやり抱えこむのも無理になりつつありました。
それでも全身の筋肉を振り絞って泣いて暴れる息子を力づくで抱えていきます。
チャイルドシートに乗せたところでベルトを着けるには片手で暴れる息子を抑え、片手でベルトをカチッとつける。一人ではとっても無理でした。(10分近く格闘していました)
ギャーギャーと響き渡る息子の声。よく通報されなかったなと思いますがきっと近隣の方は状況を察知し心配されていたと思います。
保育園に着いたら着いたで今度は車から降りたがらず、抱えようとする私の腕をすり抜け暴れ、駐車場の地面で伏せて泣いている…先生が気が付いて駐車場に迎えにきてくれたこともありました。大人が二人いればなんとか力づくで抱えていけるのですが、子どもといえども年中児、それなりの力もあるし、抱えようとすると軟体動物のようにスルっと腕をすり抜けてしまうんです。私一人ではどうしても無理でした。
登園拒否の原因
・先生がイヤ、お友達がイヤ、給食もイヤ!
息子に理由を聞いたところ、「先生もお友達も給食もイヤ、おやつだけが好き」と言っていました。
先生のどんなところがイヤなのか具体的に話すことがまだできなかったので推測になります。
年少時の先生とは違い、厳しめの先生でした。これは相性なのでどうしようもなかったと思います。年中になるとだんだんとお友達同士で遊ぶようになる年頃です。仲間に入れないことを少しずつ感じとっていたのでしょう。給食も自分で食べきることが難しく補助が必要だったのですが、厳しい先生だったのであまり手伝ってもらえなかったのでしょう。
おやつだけは手で持って食べるものが多かったので食べやすいし、なによりおやつはおいしいですものね。これだけは楽しみだったようです。
・環境が変わりなじめない
変化が苦手な息子、担任が変わった、玄関や過ごす教室も変わった、荷物を置く場所も変わった、もう一大事だったのでしょう。
・やりたくないことをやらされる
・園の活動についていけない
保育園でよく行われる折り紙や粘土や絵、工作などの制作に一切興味がなかった息子。お遊戯なども好きではありません。息子的にはなぜ、こんなことをしなくてはいけないのだろうという感覚だったのではないかと思います。手先が不器用で体幹の弱い息子はこのような活動についていくことができませんでした。
息子は虫が好きだったので、庭に出れば地面を這いつくばってアリやダンゴムシの観察を永遠にしていました。
・自由にしていたい
注意散漫、目や耳からの情報に過敏な息子は色々なことが気になってしまい集中して活動に取り組むことができませんでした。他のクラスが気になり教室へ行ってしまうこともありました。注意されることもイヤで余計に反発してしまっていたようです。
保育園が合っていない?
発達面で遅れがみられ、こだわりなどもあった息子は自閉症スペクトラムの診断がおりていました。
入園前に発達障害があることを園に伝え、了承いただいた上で通園しています。
様々な活動に個別の支援が必要となっていた息子は、通常の保育園で毎日過ごすには辛く楽しくなかったのでしょう。とはいえ昨年までは毎日通えていたので保育園が全く合わないわけではなかったと思います。保育園は優しい先生が多く、温かく息子をうけいれてくれている。でも、もう明日からは保育園にも仕事にもいけないかもしれない…退園することはなんとか避けたかったです。
前々から考えていた療育の利用を検討することにしました。
登園拒否の対策
保育園側の対策
・門をくぐってしまえば大丈夫
「来てさえもらえれば大丈夫なんですよ」と園長先生に言われました。しばらく泣き続けていても、ある程度時間が過ぎるとあきらめてその後は泣きもせずに過ごせていたそうです。ちなみにしばらく泣いている時間は40分位と言っていました。あの声量で泣き続けるのを面倒みるの大変だったでしょう、先生には頭が下がります。
とはいえ、その「連れていくことができないからこちらは困っているんです」と心の中で訴えていました。私だって園の門さえくぐれればこっちのもんだ!と思っていましたから。
とはいえ、迷惑がらずに「連れてきてもらえればこちらに任せて」という園側のお気持ちはありがたかったです。
・ある程度は好きにさせる
息子が通っていた園では朝、庭遊びをしてから教室に入るのですが、虫の観察が好きな息子は教室に入る時間になっても指示を聞かず、ひたすら庭を這いつくばっていたようです。ある程度は好きにさせ、時計の針がここになったら教室に入るよと約束をさせることで対応してくれていたそうです。
他のクラスに遊びにいってしまっても、先生同士で連携を取り受け入れてくださり、他のクラスのお友達も「○○くん(息子)、きたね~」とウエルカムな雰囲気でむかえてくれたそうです。
フリーの先生についてもらう
保育園側の都合で当時は加配の先生がつくことはできなかったのですが、できる限りフリーの先生についてもらい息子に個別に対応してもらっていました。
週に一度休む日を決める
頑張って連れて行っても3日目には「行かない」と大暴れしてしまうので、思い切ってはじめから週に1日休む日を決めました。平日に休むことで仕事は大変でしたが、急遽休むよりはマシでした。何より朝から「行く」「行かない」と戦わなくて済むのでお互いのストレスも減りました。
おばあちゃんと過ごす
週に一度平日に仕事を休むのは毎週は難しく、実家の母に来てもらい、一日息子と過ごしてもらい私は仕事へ行くことができました。
母はもちろん事情は知っているので保育園のことは何も聞かなかったそうですが息子は「今、保育園なにしてるかな」と話していたようです。イヤで休むとはいえ気になっていたのでしょう。
大好きなおばあちゃんと過ごすことで安心し気持ちが落ち着いていたようです。
パパが送っていく
パパは早い時間に出勤していたので私が送迎するしかなかったのですが、私の女一人の力では連れていくことができず、パパが強引に抱えて連れていくことにしました。パパは幸いフレックス勤務が使えたので、しばらくの間遅れて出勤していました。泣いて暴れる息子を強引に車に乗せ、ベルトを締め、「うわ~ん、パパ~、降ろしてー、行かない~」と号泣する息子の声を聞きながら遠ざかる車を見送って胸がぎゅっとなったのを覚えています。
あまり良い方法ではないと思いますが当時はこうするしかなかったです。
しばらくするとあきらめたのか、泣かなくなってきました。
パパもずっとフレックスを使うのは仕事に支障が出るというので落ち着いたタイミングで再び私が送迎することにしました。
登園拒否の対策 失敗編
息子には失敗した作戦ですが、もしかしたら成功するお子さんもいるかも?と思いご紹介します。
・ご褒美をあげる
①園に着いて車から降りるのを渋っているときに「元気のでるグミ食べる?」と息子の好きなグミを用意しました。「うん、食べる」ともぐもぐ食べる息子。「元気出た?」「うん」「じゃ、行こうか」「イヤだー、行かない」大失敗でした。
②私「保育園から帰ったらこのお菓子たべようか」
息子「行かない」
ごほうび作戦はイヤでしかない息子にとっては単なる子どもだまし。通用しませんでした。
虫を見に行こうか
園の駐車場でしぶる息子に大好きな虫で誘い、園の門をくぐろうという作戦でしたが大人の手の内は分かっている息子。
その作戦には乗らず「行かない」でまたしても失敗でした。
ドライブする
園に着き車から降りたがらないとき、その場で「行く」「行かない」の攻防戦を繰り広げるよりはドライブすれば息子の気分が変わるかも…と思いましたが気分が変わることなくドライブしたことで園にも仕事にも遅刻するだけでした。トホホ…
登園拒否の解決方法~わが家の場合~
発達障害のある息子には通常保育が厳しかったのだと思います。
そう思うとずいぶんかわいそうなことをさせてしまったと思います。
以前から療育を利用した方がよいのではないかと考えていた私。
療育へは息子と一緒に見学し、自由で楽しそうな雰囲気が気にいった息子は、ここに通いたいと、目をキラキラさせ週に3日は保育園、週に2日は療育(1日型)と通う曜日も息子が決めスムーズに利用開始となりました。3日間は保育園でサポートしてもらいながら頑張り、2日間は楽しくリフレッシュできることが励みになったのか、保育園へは拒否も渋ることもなくスムーズに登園できるようになりました。
もともと発達障害の診断を受けていて病院にも定期的に受診し、月に一度作業療法を受けていたので比較的手続きはスムーズにいきました。
利用した療育は集団課題や個別課題もあり、割合プログラムがしっかりしている療育でした。かといって厳しいわけではなく、少人数で先生のサポートも手厚い点では息子には合っていたのだと思います。
登園拒否・しぶりが起きたら…解決するためには
・原因を探る(本人と保育園に聞く) ・保育園と相談、園でできる対策をしてもらう ・家庭でできることは何か考える
何より行きたくない原因を考えましょう。本人に聞いたり、保育園側と相談し生活の様子を聞きましょう。原因を考えたうえで園でできることをしてもらいましょう。
園だけでなく家庭でできることは何かも考えましょう。
息子はパパ大好きっ子ですが、朝早く出勤し、夜遅く帰っているパパと触れ合う時間が少ないのです。お休みの日は息子のしたいことを優先し目いっぱい楽しく過ごすことを意識しました。
保育園に行けたことを何より褒めました。最初は無反応でしたがそのうちには「そう?」とまんざらでもない様子で褒められて少し嬉しそうでした。
現在小学1年生の息子。登校にはまだ付き添いが必要だけど、登園拒否が嘘だったかのようにとても頑張って通っています。
まだまだ学校生活はじまったばかり、これからも困難なことがあるかもしれません。
どん底に陥った登園拒否のあの頃が懐かしい思い出となるよう、息子がこれからも大きく成長できるようサポートしていきたいです。
今回はわが家の息子の登園拒否の経験について記事にしました。各お子さんやご家庭の状況によって様々ですし一概にこうしたら解決できるよ!というものではないと思います。
ですが、この記事を読んで悩んでいる親御さんの少しでも参考になれれば幸いです。そして親御さん自身の心も大事に、お互い育児を頑張りましょう。